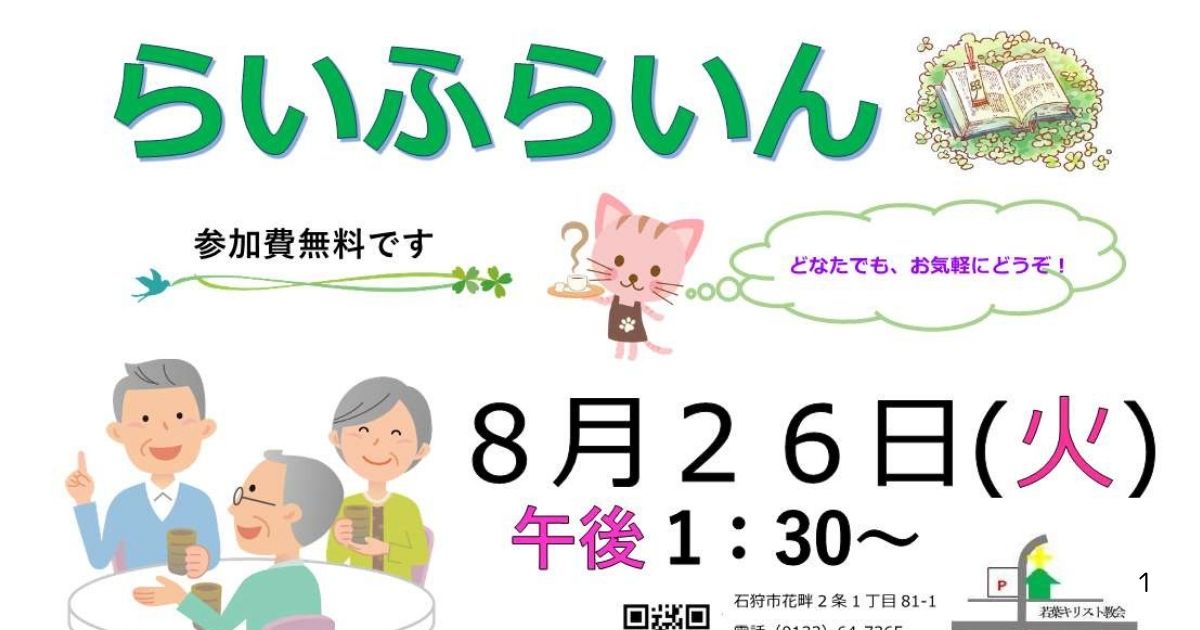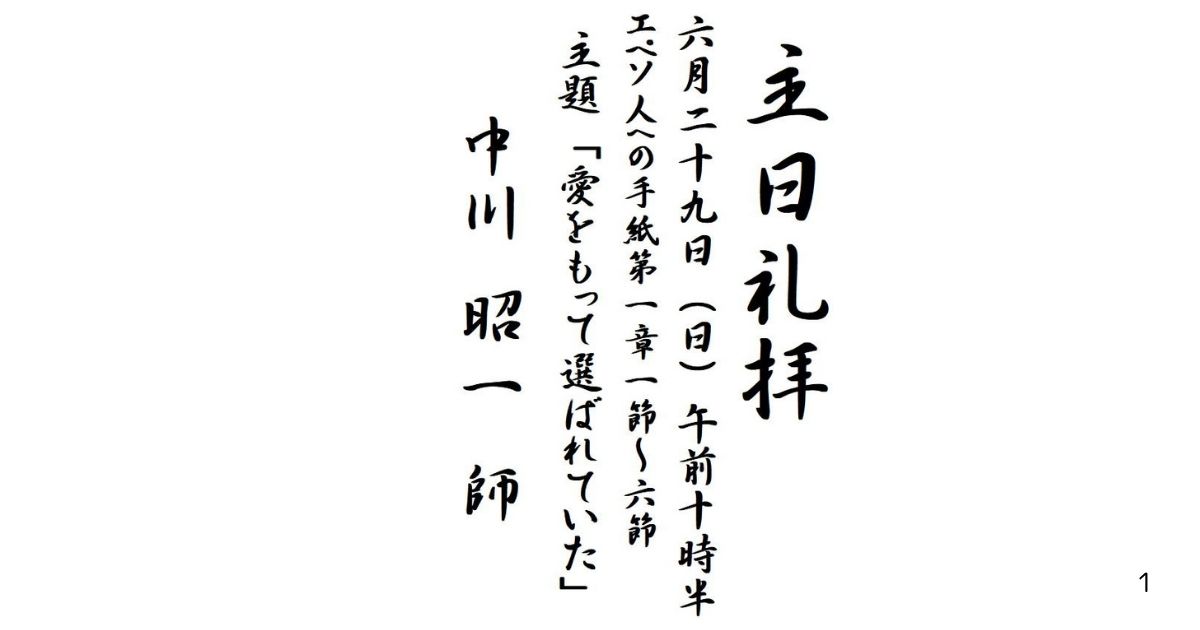特別伝道礼拝

1
/
5
2025年4月27日伝道礼拝
2024年11月24日伝道礼拝
2024年6月30日主日礼拝
1
/
5
クリスマス燭火礼拝

1
/
2
クリスマス燭火礼拝 2024年12月24日
2023年12月24日クリスマスイブ燭火礼拝
2022年12月 24日 燭火礼拝
1
/
2
若葉キリスト教会

札幌市の北隣の石狩市にある教会です。1980年9月OMFシュミット師夫妻が開拓を開始、1981年5月設立。これまでに10数名のOMFの宣教師の協力があった。地域にある教会として宣教に生きていきたい。いつも日曜の主日は、40名くらいの方が礼拝に集っています。穏やかで温かい雰囲気の中で、共に集い礼拝や集会が行われています。キリスト教や聖書に興味がありましたら、ぜひ一度、足を運んで見て下さい。聖書、讃美歌は教会に備えてありますのでお持ちにならなくても大丈夫です。あなたのお越しを心からお待ちしております。
「平和を知らせ、幸を知らせ、救いを知らせる教会」
行事の紹介

スクロールできます
| 日曜礼拝 | 日曜 10:30~12:00 | 毎週40名くらいが集まります。 |
| 教会学校 | 日曜 9:00~10:00 | 赤ちゃんから高校生までが対象です。幼少科と中高科の2クラスがあります。 |
| 朝の祈り会 夜の祈り会 | 木曜 10:00~12:00 木曜 19:30~21:00 |
アクセス
スクロールできます
| 住所 | 〒061-3282 北海道石狩市花畔二条1-81-1(バンナグロ) |
| wakabachurch1@gmail.com | |
| JR手稲駅よりバス | 麻14/麻15/麻17/宮47/:花川北6条1丁目降車 徒歩1分 |
| 地下鉄麻布駅よりバス | 麻15/16/麻16 花畔団地線[北海道中央バス]:花川北6条1丁目降車 徒歩1分 |
| 車の場合 | Googleマップ参照。国道337経由でほとんど、渋滞がありません。 教会駐車場30台(道路挟んで真向かい) |
アルバム





当教会は、統一協会(世界平和統一家庭連合)/ものみの塔(エホバの証人)/モルモン教/摂理などとは関係は
有りません。 お困りの方はご相談下さい。